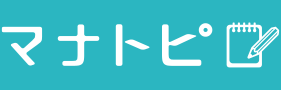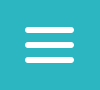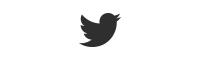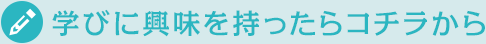医療現場の即戦力、看護助手
医療現場で活躍する看護師は、多くの人を助けるやりがいのある仕事で、時代を問わず人気が高い職種です。しかし、看護師になるためには国家資格が必要で、大学や専門学校などに3~4年通学しなければなりません。
一方、同じ看護の現場で看護師をサポートする「看護助手」なら国家資格は不要で、未経験者可の求人も多くあります。ただし未経験者でも働けるとはいえ、全く知識がないと、病院で使われる専門用語や患者さんとの接し方などに戸惑ってしまうかもしれません。不安な方は、看護助手として働く際に知っておくべき内容が身についていることを証明する「看護助手実務能力認定資格」の学習をすると良いでしょう。
看護助手講座なら、修了すれば「看護助手実務能力認定資格」が申請のみで取得できるので、外出が難しいママはぜひ活用しましょう。即戦力としての知識や技能が身につくだけでなく、資格があれば就職活動でもアピールできるでしょう。看護助手を目指すなら、資格取得は近道になるはずです。
看護助手講座へのリンク
安定した仕事環境が魅力の医療事務

医療機関で患者さんの接遇・受付・治療費の会計・レセプトの作成などの事務全般を行う医療事務。安定した仕事環境で長く勤めやすく、出産後や育児中でも働きやすい職種として広く認知されています。
医療事務自体は資格がなくても従事できますが、ルールに基づいたレセプト作成業務など、専門的なスキルが必要になる仕事には変わりありません。未経験で医療事務の仕事に就きたいと考えている方は、資格を取得して、実務に必要な知識とスキルを学んでおくのがオススメです。
また医療事務資格の学習をするには、通信教育が便利です。ユーキャンの医療事務講座なら、4ヵ月という短期間で知識を身に付けられるうえ、在宅受験も可能なので、小さい子どもがいるママでも挑戦しやすいでしょう。
医療事務講座へのリンク
高齢化社会を支える「准サービス介助士」

公共施設などの街中で、高齢者や障がい者をサポートできる知識を身に付けた人材、それが准サービス介助士です。入浴・排泄・食事などの介護が不要な、比較的元気な高齢者や障がい者のお手伝いをします。
准サービス介助士からさらにステップアップした資格に、サービス介助士があります。准サービス介助士とサービス介助士の違いは、「介助の技術」を学ぶかどうか。准サービス介助士の場合は、配慮を必要とする人への「おもてなしの心」と「介助の知識」を学びますが、サービス介助士の場合は、2日間の実技教習で「介助の技術」も学びます。
忙しくて実技教習の時間が取れない人や、まずは介助の知識を身に付けたいと考えている人は、実技教習が不要で在宅受験できる『准サービス介助士』から目指すと良いでしょう。
准サービス介助士講座では、家庭内や外出先での介助の仕方を主に学び、配慮が必要な人への手助けを適切に行うための知識が身につきます。修了すればそのまま資格を取得できるため、短期間で集中して資格を取りたい人には最適です。
准サービス介助士に合格すると、サービス介助士になるための提出課題が免除されるなど、ステップアップも有利になります。
准サービス介助士講座へのリンク
注目の新資格、レクリエーション介護士
介護施設などでは、高齢者の方が楽しみながら気軽に体を動かしたり頭を働かせたりするレクリエーションを行っています。これらを企画・実施するのも介護士の仕事ですが、レクリエーションは内容や進め方を決めるのが意外と難しいものです。
そこで今注目されているのが、2014年に誕生した資格「レクリエーション介護士」です。介護とレクリエーションそれぞれの知識を修得し、安全で楽しいレクリエーションを提案して、介護する人・される人双方の暮らしの質を高めるスキルを身につけます。
レクリエーション介護士講座では、安全で楽しいレクの具体的なアイデアや、実施方法などが学べます。また、「人をサポートしながら楽しむ」というスキルは、介護だけでなく幅広いことに応用できるでしょう。こちらも自宅で取得できる資格なので、産休・育休中の取得に特に適しています。
レクリエーション介護士2級講座へのリンク
通信講座で産休・育休中も自分磨きを!
今回は産休・育休中でも取得しやすい、医療・福祉関連の資格についてご紹介しました。長い休暇に入り、忙しく働く毎日から急に変化したゆとりある暮らしの中で、キャリアアップや自分磨きのための勉強を志すのはとても良いことです。産休・育休からの復帰後も、家庭と両立しながら社会で活躍したい方は、自分のペースで進められる通信講座で医療・福祉関連の資格取得をぜひご検討ください。