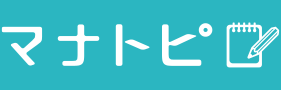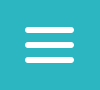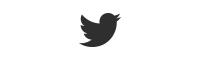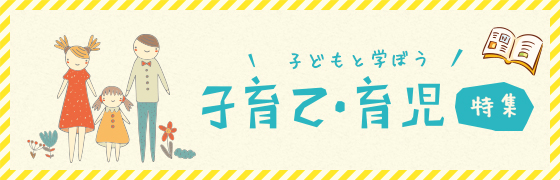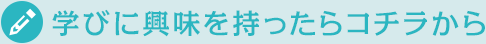でこぽん吾郎さんが語る「保育士ってこんなにおもしろい!」

子どもたちから愛され慕われる男性保育士 “でこ先生”を主人公として、保育士時代の経験をベースにマンガを描いているでこぽん吾郎さん。でこ先生と保育所の子どもたちが織り成す笑いあり涙ありの日常は、Twitterで最高16万超のいいねが付くほど大人気です。
そんなでこぽん吾郎さんが保育士になったきっかけは、「子どもの頃に通っていた園の担任の先生が大好きだったから」だとか。
「おんぶしてもらったことや、褒めてもらったことをずっと覚えていたことに加え、私自身、子どもが大好きだったので、“いつか保育士になりたいな”という思いがありました。大好きな歴史や美術の分野に進むことを考えた時期もありましたが、“子どもが好き!” “保育をやってみたい!”という思いが勝り、保育士になったんです」(でこぽん吾郎さん)
実際に保育士となり、さまざまな経験を重ねていったでこぽん吾郎さん。ときには苦労したこともあったかと思いますが?
「大変だったのは、仕事量の多さです!日々の保育、書類、環境整備……、挙げていくとキリがないです。何度、“分身の術を使えるようになりたい”と思ったことか……。また、“保育には正解がない”ということにも驚きました。本当にさまざまな考え方ややり方があって、駆け出しの頃は“どれが正解なんだ〜?!”と、軽くパニックになることもよくありました(笑)」(でこぽん吾郎さん)
一方で「保育士で良かった」と感じた思い出も、たくさんあるそうです。その一つが、初めて担当した5歳児クラスの卒園式で、保護者の方々から花束のプレゼントをいただいたこと。
「卒園式の練習のときから、子どもたちと一緒に号泣しながら練習していた私ですが(笑)、本番で無事に式が終わり、保育室に戻ったときのことでした。私から子どもたちと保護者の方々に挨拶をした後、サプライズで花束をプレゼントしていただいたんです。最後は泣かずに、冷静に振る舞おうと思っていたのですが、全然無理でした。涙腺崩壊(笑)。“がんばって良かったな” “保育士で良かったな”と思った瞬間でした」(でこぽん吾郎さん)
では、でこぽん吾郎さんにとって、保育士という仕事の魅力とは?
「いろいろあって迷いますが、やっぱり、子どもの成長を毎日見られることですね。子どもって、日々変化しているので、成長に気付けたときは本当に嬉しいです。“なんだか、一つのドラマを見ているようだなぁ”と、思うことも多々ありました」(でこぽん吾郎さん)
マンガで紹介①保育士っておもしろい!
日々、成長する子どもたちの一挙手一投足に、保育士としての喜びを見出していたでこぽん吾郎さん。ときには予想もつかない行動に驚きや発見を感じながら、「保育士っておもしろい!」と実感することも多かったとか。そんな毎日が垣間見えるエピソードを、でこぽん吾郎さんのマンガでご紹介しましょう!
【第27話 未来予知】

(でこぽん吾郎先生Twitterより)
保育士になって初めて気付いた、子どものリアルと自身の成長

保育士として子どもと触れ合っていくうちに、さまざまなことに気付いていったという、でこぽん吾郎さん。
「いざ保育士になってみると、子どもの成長やいろいろな可能性、予想外のおもしろい行動など、さまざまな姿が見えてくるんです。そうやって理解していくことで、“子どもが好き!”という思いはさらに深まりましたね」(でこぽん吾郎さん)
こうした日々は、自分自身にも変化を及ぼしたそうです。一つは、子どもへの接し方。
「“今、この子はどうしたいのかな?” “何を感じているのかな?”と、子ども目線で考え、気持ちに共感しながら接することができるようになりました。子どもの目線で見てみると、いろいろな発見があって、おもしろいんですよ」(でこぽん吾郎さん)
そしてもう一つは、「自分を受け入れられるようになったこと」でした。
「恥ずかしながら、新人のころは自分のやり方に固執したり、完璧に仕事ができない自分を許せなかったりして、保育がうまくいかないことがよくあったんです。でも、子どもそのものが完全ではない、成長途中の存在であるように、大人である保育士も、 完全ではない成長途中の存在なのだということに気付くことで、できない自分、まだまだな自分を、少しずつ受け入れられるようになっていきました。振り返ってみれば、子どもを育てているようで、実は自分が育てられていた気がします。私を人として育ててくれた保育という世界の懐の深さ、温かさ、楽しさを、いつまでも忘れないようにしたいですね」(でこぽん吾郎さん)
マンガで紹介②保育士は見た!子どものリアル
多くの子どもが成長していく中で迎えるのが、イヤイヤ期。あれもこれも「イヤ!」を連発する子どもたちにどう接すれば良いのかも、でこぽん吾郎さんのマンガは教えてくれます。先生ならではの秀逸なオチにも、どうぞご注目を!
【第81話 パンツ屋さん】


(でこぽん吾郎先生Twitterより)
では最後に、保育士を目指す方へ、でこぽん吾郎さんからアドバイスをお贈りいただきましょう。
「最初は分からないことや不安なこともたくさんあると思いますが、大丈夫ですよ。保育はある意味、“技術職”です。先輩や同僚、後輩の保育で参考になる技は、どんどん盗んで実践しましょう!必ず自分の身になります。また、子ども一人ひとりが大切な存在であるように、保育士一人ひとりも、かけがえのない存在です。保育士になってからも、ご自身の心と体の健康にはしっかり気を配りながら、保育をしていただきたいなと思います」(でこぽん吾郎さん)