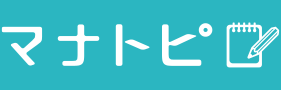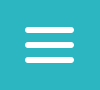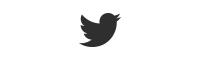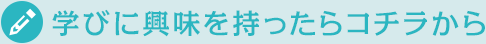30分で菌が急増! 買い物をしたら寄り道は厳禁!

スーパーマーケットで食材を買うときから、食中毒対策はスタートします。食中毒の細菌は、10~45℃の温度で生育し、特に30~37℃を好むのだとか。食中毒を防ぐためには、お買い物中、以下のことに注意しましょう。
<買い物中>
・食材を買う順序に注意し、生鮮食品は最後にかごに入れるようにしましょう。生鮮食品は常温に放置したままだと、たった30分で菌が急増するというデータもあります。
<お会計後>
・肉や魚はパックごとにビニール袋へ入れましょう。肉や魚の汁が他の食品に付着し、細菌感染するのを防ぎます。
・最近では氷を常備しているスーパーマーケットも増えてきました。ぜひ氷をもらい、食材の温度を上げないようにしましょう。その際、保冷バッグを利用するのも効果的です。
・お店を出たら、できるだけ早めに帰宅して、買ったものをすぐに冷蔵庫へしまいましょう。冷蔵庫の中は詰め過ぎないようにし、効率よく冷気を循環させます。
この時期、「一晩寝かせたカレー」はとっても危険!

食中毒予防のポイントは「75℃で1分間加熱」ですが、加熱すれば十分というわけではないのが食中毒の恐ろしいところ。たとえば2014年の1年間に約2,400人が感染したウエルシュ菌は熱に強く、カレーなどの煮込み料理でも繁殖しやすいという性質を持っています。
特に危険なのが、2日目のカレー。空気を嫌うウエルシュ菌にとって、空気が入ってこないカレーの鍋の中はとても住みやすい環境。また、43~47℃になると爆発的に増えるという性質もあり、とろみがあって熱が冷めにくいカレーの鍋は、まさにウエルシュ菌の楽園! 8時間後には281兆倍に増殖するというデータもあるので、十分な注意が必要です。
カレーを作ったあとは常温で放置せず、小分けにして冷蔵庫へ入れましょう。そして食べる前には、しっかり加熱しながらよくかき混ぜてからいただきましょう。
"お弁当”も要注意! 食材は冷めかけのときに菌が発生しやすい!

ダイエットや節約のために、手作りのお弁当を会社に持参する人も多いはず。でも、梅雨の時期には注意が必要です。食中毒の多いこの時期に、気をつけたいお弁当作りのポイントを紹介します。
■おかずのチョイスに注意! 湿気と水分管理を徹底
食材はしっかり火を通すことが大切ですが、同じくらい大切なのが、よく冷ますこと。冷めかけの温度のときに細菌が繁殖しやすくなるので、おかずの熱や湿気がとれるまで、お弁当のフタを閉めないようにしましょう。特に冷めにくいご飯は、詰める前に一度浅めのお皿などに広げて、熱を取っておきましょう。
また、水分があると細菌が増えやすくなるので、おひたしや煮物など汁気の多いおかず、水分が残っている生野菜などは避けた方が無難です。
■意外と見落としがち。お弁当の容器も清潔に
意外と見逃しがちなのがフタのパッキンの部分。よく洗わないと菌が残り、繁殖しやすいので、清潔に保つように心がけましょう。
酢を含ませたキッチンペーパーでお弁当箱を拭いておくと、除菌効果が期待できます。
■傷ませない! おかずを詰めるときのコツ
容器の中でおかず同士がぶつかり、形が崩れると傷みやすくなります。アルミのカップに入れたり、バランで仕切ったり、おかずが触れ合わないようしましょう。
殺菌効果のある梅干しは、ご飯の上にのせるよりも中に混ぜ込む方が効果的です。
■保存温度にも気をつけて。お昼まで安全に保存するには?
お弁当箱と一緒に冷却材(保冷剤)を入れて、暑さでお弁当が痛むのを防ぎましょう。保冷剤と一緒に包むときには、お弁当箱の上に置くのがおすすめ。冷気が下に流れ、効率的に冷やすことができます。
また、市販の一口サイズのゼリーなどを凍らせて詰めることで冷却剤として活用することもできます。デザートとしても楽しめ、一石二鳥です!
毎日の健康管理は食生活がポイント